慈光院からの帰り道、
慈光院の見学が心地よかったからか、
ちょっと遠回りになるけど…と、
酬恩庵一休寺に寄ってみることにする。
時間はギリギリだけど、なんとか間に合いそう…と。
慈光院が本当に気持ち良かったので、もう少し…という気になっていた。
だけど、特に拝観日が指定されているような施設では、
ついでに…立ち寄ってたまたま見れた…などという偶然はほとんどない。
…というか、虎丘庵は特別拝観でしか見れない…ということを忘れていた。
虎丘庵って、昔から特別拝観のみでしたっけ?
そうなんんでしょうね…。
ということで、ここまで読んで戴いて、察しが付くと思いますが、
一休寺には入れましたが、虎丘庵は見れませんでした。

綺麗な形の唐門 ↑ 。


方丈 ↑ 。

開山堂 ↑ 。

ちょっとお遠目ですが、本堂 ↑ 。


そしてこれが、虎丘庵 ↑ 。
リーフレットの説明を要約すると、
京都東山の麓にあったものを一休禅師が応仁の乱を避けるために移築したもの。
静寂穏雅な建物で屋根は檜皮葺き。
周囲の庭園は禅院枯山水のもので東部は七五三配石で、
大徳寺真珠庵の七五三庭園と同じ手法によるもので、作者が珠光と伝えられている。
現存する建物は、前田利家が修理を施していたり…と当初のままではないようですが、
「茶室」の先駆となった庵室の貴重な遺構…と中村昌生氏も書いておられますし、
見るからに書院ですけど、
同仁斎よりも格段に茶室建築へと繋がる現代数寄屋に通ずるものを感じる建物なんです。
今回は見れなかったけどね。
わざわざ遠回りをしたのに、お目当てにお目に掛かれなかった…という悲しい現実でしたが、
結果的には、
帰りに通ろうと思っていた高速道路が事故で渋滞していたようなので、
ここに立ち寄らなくても、こっち廻りで帰っていたかもしれません。
ま、ちょどよい回り道になったということで…。
ありがとうございました。
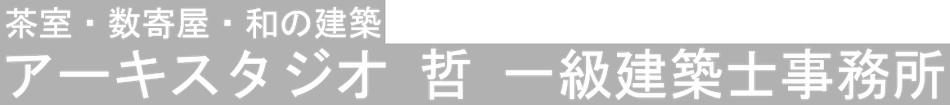
コメントをお書きください