宇治に行くことがあり、朝日焼ギャラリーへ。

ギャラリー内のお茶室が、展示スペースにもなってますけど、三畳台目の向切。
ガラリーを兼ねたお茶室ですが、
上手くまとめているなぁ…と、なかなか好印象。
ついでに、近くに京都市市営の茶室があるということで、
川を渡って拝見に。
名前は「対鳳庵」。
鳳凰堂のとなりだからかな?
…が、聞いてみると予約は外人さんで一杯。
呈茶には入れず、当然ながら小間は開けてもいなくて、見学はできず。
なんとなく想像はしていたけど…。
毎日ほとんどが外国人で、日本人は珍しい…とか。
この日はすでに二服よばれていてお茶が飲みたかったわけではないので、
呈茶は別にいいんだけど、
リーフレットを見る限り、
床の間の設えは違うけど、
点前座の正面に火灯口を開けた板を入れた有楽囲いになっていたり、
盲連子の有楽窓のような窓があったり…と、
如庵を意識したんだろうな…というお茶室で、
少しでも見たかったな…と。
残念。
あちこちでお茶室の見学に行きます。
前もって調べてから行くところもあれば、
唐突にお伺いすることもあります。
お金を払って見学できるところを除くと、
普通にお茶室を開けて開放しているところの実に少ないこと。
呈茶はやってても広間か立礼で、その隣にある小間は閉まっているとかね。
日々の雨戸の開け閉めとか、手入れとか、メンテナンスが大変なのはわかります。
日本人にもマナーの良くない方がおられることも理解しています。
だからといって、
使わないで閉め切っておくのもどうなのかな…と、いつも思います。
折角の希少な日本の建築文化の一つなんだから、
中に入るのは無理でも、
開けて、少しばかりのセッティングをするぐらいは出来ると思うんだけどな…。
その方が、空気の入れ替えになって、
建築にもいいと思うんだけどな…と。
そんな愚痴を、
私の同行者はいつも聞かされているはずです。
ありがとうございました。
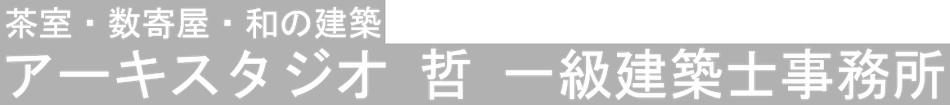
コメントをお書きください