先日の展覧会で呈茶を戴いたあと、
組立小間を拝見。
最初、
あれ?躙り口の矩手に貴人口があったかな?…とちょっと疑問に思い、
以前のお茶室を思い出しながら躙り口から中の様子を伺う。
小間内部は、台目切りの三畳…?
あれ?間取りが違う。新しいのを作ったのかな?
続いて浮かんだそんな疑問を頭の中で整理しながら、躙り入る。
中に入り、
床の間の感じは前と同じ…か。
先に中に入った知人との簡単な問答をしながら、
その後に誰も来ないのをいいことに組み立て茶室の中で少々談義。
中に居る時間が伸びてくると、
全体に拡がっていた意識が徐々に部分から細部に向きはじめ、
また、何度か見ているうちに目も肥えてくるので、
見えていなかったものも見えてくる。
これがお茶事の時の部屋の暗さなら、そんなことにはならなかったのかもしれないけどね。
少しの時間だけどそこ居て、
感じた疑問や違和感を忘れないように頭の中で整理し、
帰ってから、前の展示の写真と見比べてみる。
私の年相応(?)に少々怪しくなってきた記憶をたどると、
天井のクロスも同じだったし、
竿縁も同じ納まりだったように見えたので、
とりあえず、前の四畳半との違いを整理したくて、
見比べたのは四畳半の方。

で、ここからが私の推理…というか、妄想。
写真を見ると、
間取りは違うんだけど、
ひょっとすると、
床廻りの造作は前の四畳半のものをそのまま使ってるのかな?
…と、別の疑問が浮かぶ。
そういう目で見ると、
床の間側の一間半の壁が、すべて前の四畳半からの流用に見える。
…ということは、風炉先窓も?
前の壁面に、中柱と袖壁を付け加えただけなのかな…。
となると、
釣り棚や中柱、袖壁は不審庵の写しからの流用か?
…とも思ったけど、
さすがに、釣り棚は今回の方が少し幅広だった気がするし、天井高が違うはず。
また、中柱は今回は赤松ぽかったけど、前回は磨きだった。
袖壁の壁止めも今回は木だけど、不審菴写しは竹。
明らかに違うところもあるので、風炉先以外の点前座廻りは違うよう。
まぁこれは、
感覚だけのあいまいな話もあるし、
吊材は、不審菴の点前座の天井は掛け込み天井なので、
不審菴の天井高に四畳半の天井高を合わせることも可能で、
流用していてもおかしくはない。
材料が全く違うものは無理だけどね。
とはいえ、
「二つの組立小間を分解して、違う間取りの組立小間の茶室を作りました」
…という方が、話題性があって夢があって面白いんだけど、
その可能性を十分に認めた上で、
話がややこしくなるのを避けるために、
今回の、この私の妄想の中では排除することにします。
で、そのほかに四畳半からの流用はないかを以前の写真をみて考えてみると、
躙り口廻りと貴人口廻りの外観も前の四畳半からの流用にも見える。
貴人口の位置が違うけど、
躙り口の敷鴨居の納まりも同じだったしね。
でも、ここも流用すると出隅の柱がうまくいくのかな?
あっ!そのための付け鴨居という考え方も出来るな…と、
「なんで外側に付け鴨居をつけてるのかな?」
…と前回、現地で見ていて不思議に思っていたことを思い出した。
なるほど…。
組立とか、部材の接合とか、製作とか、材料の定尺の都合で付鴨居があるのかな…と思っていたけど、
出隅の柱の仕口の粗を隠すため…というか、
貴人口の鴨居との仕口の粗を隠すため付け鴨居があるというのも、ひとつの理由としてなくはないのかな…と。
そうなると、内側は付け鴨居無しで納まってるのおかしくない?…という声も聞こえてきそうですが、
そこはちょっと目を瞑っておこうか…。
…と、結構長い時間、ひとりで写真を見ながら楽しませて頂きました。

…で、
写真での判断の部分が多く間違ってるのかもしれませんが、
結論としては、
今回の三畳は、前の四畳半からの流用の部材で作られていて、
四畳半の床の間に向かって左右(奥行き方向)の壁の
左側の一番奥の壁と右側の一番手前の壁を半間ずつ取り外し、
一間半あった奥行を一間に縮小して、三畳にしたものだと判断いたしました。
そうすると新調するのは、
点前座の畳と炉廻りの畳、中柱とそれに取り付く袖壁と壁際の付け柱だけということになる。
それは、先に作っておけば付けるだけだしね。
↑ の妄想では、
とりあえず「不審菴の写し」からの流用はないこととしましたが、
炉廻りの畳は、もしも新調しないなら、不審庵の写しのものを使うことはできますし、
釣り棚や中柱、袖壁、その他の部分についても、
もう一方が「不審菴の写し」という冠を被っていない茶室であれば、
十分に流用可能に造れます。
が、ここは結果的に、
最初から四畳半と三畳の両方が組めるように設計されていた組立小間だった、
ということにして終わりにします。
あくまでも、私の妄想ですからね。
もし、この展覧会に行かれて、この話に興味がある方はそういう目で見れば面白いですよ。
↑ の言葉での説明だけじゃわからないかもしれませんし、
元の四畳半を見てないとわかり難いとは思いますが…。
もし必要なら呼んで戴ければ、もう少し細かく私の考えを解説しますよ。(笑)
室内空間に関しては、
これも全くの個人の意見ですが、
パンフレットの写真を見た時からのちょっとした違和感が気になっていて、
実際に見ても、やっぱりそこは気になったので、
四畳半の場合の方が違和感がなかったように思います。
現地で見た時には、流用の話は思い当たっていないので、
単純に四畳半の方が良いな…と思っていましたが、
↑ の私の妄想が正しいとすれば、
流用するための作る側の妥協というか、もどかしさも十分に理解できるので、仕方のないところもあるか…と。
それよりも、妄想で遊ばせて戴いたことに感謝…です。
私の妄想に過ぎない…ので間違ってるかもしれませんが、
最初から考えておけば十分に成り立つ話ですよ、この話。
ありがとうございました。
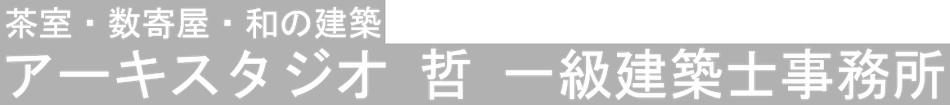
コメントをお書きください