松花堂庭園・美術館の三つのお茶室を見学。
まずは『松隠』。
HPによると、
『数寄屋研究の第一人者・中村昌生先生が設計した茶室。九畳の広間では、月釜会や松花堂忌茶会など主要な茶会で使用しています。また四畳台目茶室「閑雲軒」は、小堀遠州が松花堂昭乗のために建てた茶室を再現したものです。』

9畳の広間と4畳台目の不思議なお茶室。
9畳の方は、ちょっと高床ぎみで、眺めが良くて、心地よさそう。
こっちはそう不思議でもない。
いや、やっぱりこっちも少し不思議で、
本間は6畳。
そこに2畳の広縁がついて、
あと1畳は、表千家や久田家の7畳のように、
1畳分飛び出して、合計9畳。
だから、例に出した7畳とおなじで、
花月が出来ない造り。
ここでやるかどうかは知らないけどね。



…で、
もうちょっと不思議なのが、「閑雲軒」と名のついた4畳台目。
簡単に言うと、4畳台目の小間の廻りに屋内の廊下が廻っていて、
お茶室が「入れ子」のようになってるお茶室。



天井は、平天井が菰かな?
点前座と下座側が掛け込み天井。
雲雀棚付き。
窓多め…だけど、入れ子だから調節できるか…。
測ってないので微妙ですが、
躙り口が縦長に見えるのは背が高いのか?幅が狭いのか?写真の映りの問題なのか?
個人的な感覚として、
通常の躙り口ではなく、廊下などの同じレベルから躙って入る躙り口の場合は、
少し高めにした方が出入りがしやすいと思ってるのですが、
そうなってたのかな?
で、こんな小間の廻りを ↓ 、


↑ 小間の廻りにこんな廊下が廻る。
小間が外に面していないので、
外に面している時と比較すると、管理が少しは楽だろうし、
劣化の速度もかなり違うだろうな…とは思いますが、
外と内の区別を感覚がどう判断しているのかはわかりませんが、
廊下から小間への入り口が、躙り口と茶道口と給仕口…のみなので、
ちょっとした違和感があり、不思議な感覚を覚えました。
躙り口の必要あるのかな?…と。
あと、4畳台目だけど、あまり広さが感じられなかったのはどうしてなのかな?
何度か行ってみないとわからないかな…。
茶室そのものというよりも、
それが「入れ子」になってることで、
かなり感覚的な狂いが生じていたような気もします。
ありがとうございました。
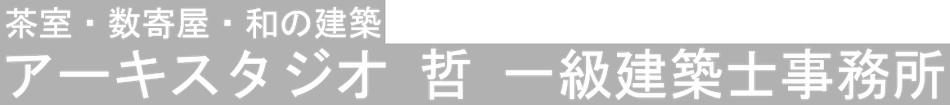
コメントをお書きください