建築をやっていると、よく見学にいく。
「見学」…の意味を考えると、
簡単に言えば「見て学ぶこと」。
意味を踏まえた上で、ちゃんと見学しているか?…と聞かれると、
答えに窮することも多々あり、
見て学ぶ…の後半が飛んでしまっていて、見るだけになっているケースも少なくない…というか、
その方が多いのかもしれない。
ただ私は、見学…ということに関しては、
それでいいと思っている部分もあって、
見て学ぶ…というか、見て感じること、
建築に限って言いうと、目で見て、空間体験して、感じること…が一番大事だと思っている。
そういう意味では、
建築の見学は大事なところに入れず、
見るだけの空間体験が出来ない見学コースになっているケースが少なくないのが痛い。
そういう意味では残念だが、それは建築を守る上では仕方がない場合が多いのも理解ができる。
ただ、見せ方を工夫することは出来ないものか?
見学する側の勝手な意見だが、
開口部を開放し、開放した開口部から中が覗ければそれでいいのか?
とか、
その建築がそこにある…ということに胡坐をかいているんじゃないか?
…といった感情が沸くときがある。
古い建物になると、ただ漠然と見せるだけでは、建築の傷みばかりが目立ち、
見方によれば、傷みの烈しいそれを見せられて逆に興味を欠くことだってあり得る。
実際には、どんな明るさの環境で、どういう使われ方をしているのか?…が知りたい。
常にその場を実際に使っている環境に整えろとは言わないが、
いまはいろんな技術もあるし、動画だって簡単に撮って簡単に編集が出来る時代。
映像表現も加えて…という方法をはじめ、考えればいろいろ考えられるはず。
それと、まだ見学のために開放しているからマシだが、
建築というのは、使わなければ使わないだけ傷みが激しくなる。
使ったら使ったで傷むじゃないか?と言われることもあって、
難しい面があるのを承知で書くと、
使っての傷みは使う側の気遣いで何とかなるし、
粗っぽい使い方をする人には貸さないことや、丁寧に使う教育も出来るはず。
なんとか、使いながら維持する方法はないものだろうか?
建築は、その方が生き生きとした見え方となり、
なんとなく、傷んでみすぼらしく見える建築を見せられるより、
より興味深いものとして見えるはず。
ただ、見せているだけで、
見せていることが価値…という見せ方が本当に正しいのか?
各地の歴史的建築の見学料もそれなりに上昇し、
それなりの金額を支払って見学した建物が、
実際には朽ち果てる寸前…ではないにしても、
少なくとも、そのぐらい傷んで見える場面に出くわすと、
少々胸が痛く、
折角払った見学料で、
もう少しなんとか出来ないものか…と考えてしまうのです。
これは、建物が古い新しいではなく、愛情の問題なのかもしれませんが。
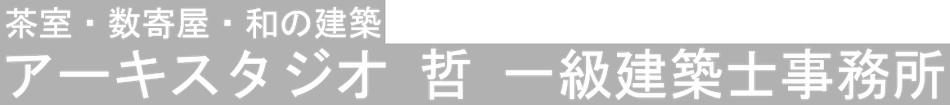
コメントをお書きください