続いて 『竹隠』
こちらもHPをみると、
『江戸時代から4代続いた京都の数寄屋大工・木村清兵衛が建てた茶室の写しです。四畳半の茶室で、琵琶床が特徴です。』

外観はオーソドックスに茶室っぽくて、
全体に、奇をてらわない雰囲気がいい感じ。

お茶室は、四畳半切のオーソドックスなお茶室。
小間使いも広間使いも出来て、使い勝手も良さそう。




天井は、下座側が掛込天井で、あとは杉の羽重ねの平天井。
化粧垂木の材料はよくわからなかったけど、
下り壁の壁止めは香節かな?
掛込天井は、
芽付き竹に、女竹の掛蔓竹と小舞、化粧野地は枌板。
突き上げ窓付。
楊枝柱にヌリマワシ…と、
茶室的要素も盛りだくさん。
…と、全体的には良い感じ。
でも、気になるところが一つ。
床の間廻りのバランスがちょっと…。
茶室って、
点前座正面の半間の壁、または床の間の扱いが非常に難しいので、
気持ちはわからないではないんだけど、
なぜ、袋床したんだろう?
そして、袋床にした上で、なぜ琵琶台を付けたんだろう?
そして、袋床にしたこと、琵琶台を付けたこととはあまり関係なのだが、
結果として、
なぜ軸釘を床の間の大平壁のセンターにして、
見た目のセンター(床柱と琵琶台後ろの柱のセンター)にしなかったのだろうか?
建築的な面からのみの見方では、その使い勝手に大差は感じないのですが、
茶室として床の間の飾りに意識を向けてみると、
この芯がずれた感じの床の間が、
ちょっと使い難く感じてしまう人も多いような気がします。
あと、ちょっと下がり壁が私の感覚ではおおきいかな?
でも、逆に言うと、それが気にならないなら、
いいお茶室かと…。
ありがとうございました。
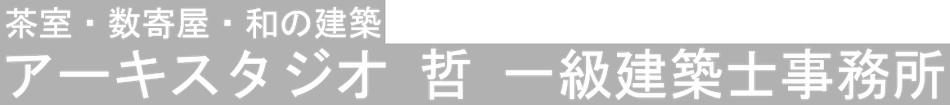
コメントをお書きください